

前回記事で述べてきましたように、苦難の乗り継ぎを経ながら、ようやく五華熱鉱泥温泉へとたどり着きました。この付近は小さな温泉街が形成されており、他にもいくつか小さな温泉宿があるのですが、中国の安宿はいろんな意味で不安なので、ここは無難に、他宿より群を抜いて規模の大きな「五華熱湖熱鉱泥温泉山庄」を選ぶことにしました。
元々無事にたどり着けるかどうかわからなかったですし、予約の方法すらも判然としなかったので、まずはフロントへ飛び込んで泊まれるかどうか確認し、どんな部屋なのか内部を見せてもらったところ、まぁ可もなく不可もなくのごく普通な部屋でしたので、安宿で冒険するよりこちらの方が無難だろうと判断して、計画通りにここで一晩を過ごすことにしました。表向きは国際的な施設であることをアピールするためか、フロントの壁にはニューヨークやロンドンなど世界主要地の時刻を示す時計が括り付けられているのですが、そこで対応するスタッフのお姉さんはインターナショナル感が一切ゼロで、英語は全く話せません。しかしながらそれを補うだけの親切心はあり、幸いにして私が日本人(つまり漢字がわかる人種)であることがわかると、お姉さんは積極的に筆談し、彼女の手によってA4のコピー用紙にびっしりと諸々の説明文が記されたのでした。お姉さん、ありがとう!

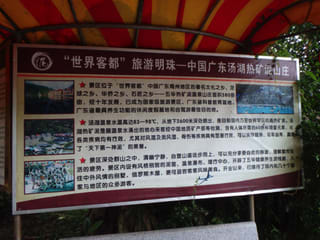
駐車場には施設の存在を示す大きな看板が立っており、「泥」という文字とともに、湯泥を塗りたくって笑顔を見せる水着の男女の姿が写っていましたが、何年前のものなのかすっかり退色しちゃって、その笑顔が却って不気味に思えました。
この施設のみならず、梅州市一帯では「世界客都」という文字を頻繁に見かけるのですが、これは当地が世界中のお客さんを迎える都市だということではなく、梅州は世界中に散らばる客家の人々のホームタウンですよ、という意味です。ご存知の方も多いかと思いますが、漢民族と一口に言っても、たとえば北京など北方の系統、上海などの呉越(江浙)系、福建や台湾などの閩民系、香港や広州などの広東系などのように、地域によって系統(文化や言語など)が分かれており、北京官話(普通話)と広東語が完全に別言語であることは有名な話ですが、客家もそうした系統のひとつに分類されながら、長い歴史の中で戦乱から逃れて流転の運命を辿ってきた関係で、自分たちの文化の源流地となるべき場所が失われており、中国各地へ散らばりつつも独自の文化を守って生活しています。そんな状況下、現在客家の人々が多く集まっている地域のひとつが、この梅州一帯なのです。この他、同じ広東省では恵州も客家人口が多いですし、海峡を越えた台湾では新竹や苗栗あたりも客家の一台拠点ですね(台湾のテレビには客家専門チャンネルがあります)。いやいや、中国のみならず、客家は世界中に散らばっており、世界の華僑の3割は客家系だと言われているほど。さらには、中共の小平・朱徳・李鵬といった面々、台湾の李登輝、シンガポールのリー・クワンユー、タイのタクシン一族などといったアジアの有力政治家の他、「悲情城市」で有名な台湾の映画監督である侯孝賢、タイガーバームの生みの親である胡文虎などなど、客家系(やその血を引く家系)は世界的に著名な人物を多数輩出しており、流浪の民でありかつ有能な人材も多いという意味で「漢民族のユダヤ人」と称されることもあります。

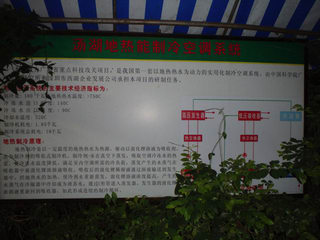
話を「温泉山庄」に戻しましょう。受付棟の前には園内図が掲示されていました。大きな池を中心にして諸々の施設が散らばっており、場所を把握しないと迷ってしまうかも。
その側にはこの施設における地熱を利用した空調システムに関する解説図と説明がなされていました。図といってもかなり簡略されており、果たしてこれで納得できる人がどれだけいるか怪しいところですが、いずれにせよ、構内の主要な建物は地熱で暖房しているんだとか。尤も、私が訪れたのは夏季ですから、暖房ではなく冷房が必要だったわけですけど…。


上述のように、敷地内に水を湛える大きな池のまわりに、温浴用の施設や宿泊用のログハウスなどがズラリと軒を連ねており、園内の庭木も手入れされていて、構内はあたかも公園のようです。
●客室


宿泊用の客室は全て「ロシア風」と銘打っているログハウスであり、収容人員によってその大きさが異なっています。ちなみに、なぜかつての仇敵であるロシアの名を名乗っているのかはわかりません。
今回私にあてがわれた小屋は、赤い屋根の小さなおうちです。


ウッディーな室内にはダブルベッドがひとつ据えられ、エアコンやテレビなど、基本的な家電品は揃っています(冷蔵庫は無かったかも)。テレビの上にはWifiのルーターみたいなものが置かれており、てっきり室内でネットが使えるものと期待したのですが、これはテレビ用の受信機器(おそらくIP放送の類)であって、ネットは使えませんし、テレビのリモコン操作も複雑で面倒でした。
木材を多用して一見温もりが感じられる室内も、ベッドの下やタンスの下など隅々までチェックすると、ホコリが溜まっていたり木が腐ってボロボロになっていたりと、不安要素がたっぷりです。訪問時は夏季ですし、この日は終日雨が降っていましたので、虫の侵入や雨漏りが心配になり、とりあえず持参していた虫除けを噴射しまくりました(ナンキンムシ棲息の痕跡が無かったことは幸いでした)。


上画像は水回りの様子です。洗面台の他、トイレとシャワーが備え付けられています。便器とシャワーが接近しているため、ここでシャワーを浴びると、どうしても便器がビショビショになってしまいます。洗面台にはドライヤーが設置されていましたが、備え付けのタオルは固くゴワゴワで雑巾みたいでした。


カランには「冷水」と「温泉水」の混合水栓で、シャワーも同様です。つまりお湯は「温泉」なんですね。どのようなお湯であるかは後ほど。
●源泉

園内の大きな池を見渡すと、畔で白い湯気をモクモクと上げているところがあります。


その場所は私が宿泊したログハウスの斜め前にあり、池へ突き出た桟橋の先に、跳ね上げ屋根の小屋と直径10メートルはありそうな大きな円筒形タンクが設けられていました。桟橋の前に立っている赤い説明看板によれば、ここは天然温泉の源泉であり、炭酸ナトリウムを含む83~98℃・pH7.79の温泉が湧出していて、泥湯や温泉プールなど各温浴施設で使っているとのこと。小屋からは温泉施設でおなじみの機械音が響いていましたので、内部には揚湯ポンプがあるのでしょう。


大きな円筒状のタンクからは湯気が朦々と上がっており、湯面からものすごい熱気が放たれていました。安全のため周囲はハンドレールが取り付けられており、しかも触れないよう水位が低く設定されていたため、直に温度計を突っ込むことはできませんでしたが、湯気の熱さから想像するに、直に触れたら火傷必至なほどの相当の高温であることに間違いありません。タンク自体は相当深く、底面は目視できなかったのですが、思わず吸い込まれそうになるほど美しいターコイズブルーの透明なお湯が、そこにたっぷりと湛えられていたのでした。
客室の水回りに備え付けられているカランやシャワーから出てくる「温泉水」はこの源泉から引かれているはずなので、シャワーのお湯でテイスティングしてみますと、ザックリ言えば無色透明無味無臭なのですが、ほのかに土類感(というか石膏感)を帯びており、アッサリ&サッパリのクセがない浴感なのですが、ほのかな土類感が密かな実力を発揮するのか、シャワー後には弱いツルスベと引っかかりが混在した肌触りが残りました。
●温泉プール




園内には豊富に湧く温泉を利用した大きな温泉プールがあり、宿泊客は滞在中(深夜以外)自由に利用できます。湯面から湯気が上がるこのプールは、鏡餅を輪切りにしたような形状をしており、半分ほどには屋根が掛けられていて、その屋根下部分はちょっと深い造りになっていました。また子供でも遊べるよう、浅い部分にはウォータースライダーも設けられています。
お湯は無色透明でほぼ無味無臭。湯度は35℃前後なのですが、場所によって多少の上下があり、温泉を供給する配管の吐出口では50℃以上の激熱状態でした。また上述において、お湯からはほのかな石膏感があったと述べましたが、スカイブルーの塗装が目立つこのプールの中で、お湯がプールサイドのグレーチングへと溢水(排水)する切り欠け部分だけはやや茶色がかったベージュ色にはっきりと染まっており、その色合いがお湯に含まれる土類の存在を窺わせていました。
なおプールサイドには上画像のようにベッドがたくさん並ぶマッサージルームもあり、リクエストすれば施述してくれるみたいですが、こんな田舎でまともな技術が受けられるはず無いので、今回は見学だけにとどめておきました。


夜は11時まで利用可能。と言ってもそんな遅い時間までプールに入っていたわけではなく、この施設構内でWifiが自由に使えるのは、フロント周辺とこのプールサイドだけだったので、ベンチに腰掛けて、あたりを飛び回る蚊に刺されながら持参のパソコンを操作し、翌日の計画を練っていたのでした。たしかに蚊は鬱陶しいものの、静かでのんびりしていて、なかなか良い雰囲気でしたよ。



話の時間は前後しますが、私がこの温泉プールへ初めて足を踏み入れた際、プールを管理しているおじさんが頻りに「瀑布へ行きなよ」とニコニコしながら勧めてきました。温泉プールの後背では湯の滝が落ちており、その滝の方へ登れるらしいのです。そこでおじさんのオススメに従い、滝へ向かってみました。途中の通路ではアドベンチャー性を高める為か、木道の階段や洞窟状のトンネルが設けられているのですが、そういうところに限ってゴミや資材の残骸が散乱していたり、ヌルヌル不衛生で滑りやすかったり、シロアリが大量発生していたりと、目を覆わんばかりの惨状。所詮ここは中国なんだと諦めて駆け足で通路を登りきると、目の前で湯の滝が飛沫をあげており、滝壺が岩風呂になっていたのでした。


岩風呂の両サイドでは石材彫刻の龍と魚が、眼下の温泉プールを睥睨していました。


この滝壺の岩風呂は小高いところにあるため、眼下に広がるスカイブルーの温泉プールはもちろん、周辺の集落(温泉街)を一望できます。岩風呂といっても、モルタルを吹き付けて岩っぽく見せているだけですが、入り応えのある深さや41℃前後の湯加減など、露天風呂としては日本人でも気に入りそうな造りになっており、景色の良さも相俟って、つい気持ち良くなって自分撮りしてしまいました。
敢えて難癖をつけるならば、肝心のお湯の鮮度感がいまいちだったことかな。この岩風呂を楽しんだ私が下の温泉プールへ戻ってくると、管理人のおじさんはプールサイドの機械室に入り、何やら操作をし始めます。間もなくプール付近で響いていた機械音(ポンプの作動音)が止まると、湯の滝の流れも徐々に弱まって、やがて流下が完全に止まってしまいました。どうやら湯の滝も岩風呂のお湯も、ポンプで循環させていたようです。なるほど、それゆえお湯から鮮度感が得られ無かったわけですが、でもこういう環境でお湯を循環させちゃうと、レジオネラ属菌が増殖しやすくなるはず。というわけで、お子さんやお年寄りはこの湯の滝に近づかない方がよろしいかと思います。私の体には何らの異状も発症していませんけど…。
●露天浴槽

温泉プールから奥へ行くと、円形の浴槽がいくつか並んでいるゾーンがありました。日本的に表現すれば、露天風呂ゾーンと言った感じです。


それぞれ形状が多少異なるものの、いずれも3~4人は入れそうなキャパがあり、42~43℃というちょうど良い湯加減のお湯が張られています。


各槽ともお湯は底面の穴から供給されており(投入口では45℃近い熱さ)、槽内の吸込口より排出されています。おじさんが湯の滝のポンプを止めた後でも、こちらではお湯の供給が止まりませんでしたから、お湯の供給に関しては別系統になっているようであり、実際にお湯の鮮度感もなかなか良好でした。実際に浴槽の温度とpHを計測したところ、42.5℃でpH8.3でした。

お湯のコンディションや温度が良く、浴槽としての造り(深さなど)もまずまずの出来。屋外にある温泉施設ではこの小さな露天風呂群が最も気に入りました。
次回につづく
.


コメント